鬼滅の刃の主人公・竈門炭治郎や禰豆子の父親である竈門炭十郎(かまどたんじゅうろう)。
炭治郎は炭十郎のことを穏やかな人と言っており、確かに回想で登場する炭十郎は、優しく微笑んでいる表情が多いですよね。
炭治郎にヒノカミ神楽を伝えたのも炭十郎であり、炭十郎も炭治郎と同じくヒノカミ神楽を使うことができました。
物語の始まった時点ですでに炭十郎は亡くなっているため、炭治郎の回想でしか登場せず、謎が多い人物の1人です。
そこで今回の記事では、炭治郎と禰豆子の父親・炭十郎について詳しく解説していきたいと思います!
- 竈門炭十郎とは何者?何が原因で死亡した?
- 炭十郎は強いの?
- 鬼殺隊との関係性はあるの?
などが気になった人は、ぜひこの記事を読んでみてくださいね。
炭治郎の父親・竈門炭十郎(かまどたんじゅうろう)とは何者?

竈門炭十郎とは、鬼滅の刃の主人公である竈門炭治郎の父親です。
物語が始まった時にはすでに故人であるため、回想でのみ登場しています。
妻は竈門葵枝(かまどきえ)で、子供たちは下記のとおりで、合計8人の大家族です!
| 長男 | 竈門炭治郎 |
| 長女 | 竈門禰豆子 |
| 次男 | 竈門竹雄(たけお) |
| 次女 | 竈門花子 |
| 三男 | 竈門茂(しげる) |
| 四男 | 竈門六太(ろくた) |
顔立ちは炭治郎と似ており、生まれつき額に痣がありました。
体が弱かったため体はやせ細っていましたが、竈門家に代々伝えられているヒノカミ神楽を極めており、雪が降る寒さが厳しい中で一晩中舞うことができました。
また亡くなるまでは、炭十郎が花札のような耳飾りを身に着けており、亡くなった後に炭治郎に渡されたようです。
炭十郎の性格
息子である炭治郎は、炭十郎のことを植物のような人と例えていました。
落ち着いて穏やかで優しい声色だったと言っています。
亡くなる直前でさえ様子は変わらなかったみたいで、家族から愛されていた人物でした。

子供たちも炭十郎に懐いていました。四男である六太は、炭十郎が亡くなって寂しくて大騒ぎする日々が続いていたみたいです。炭治郎が優しい人になったのは炭十郎の影響が大きそうです。
植物のような人と言うのは強さを表現?
炭治郎が言っていた「植物のような人」という例えですが、炭十郎の強さを表現したのでは?とも考えることもできます。
炭治郎が無限城で猗窩座の戦った時、炭治郎は透き通る世界を会得。
そして透き通る世界を会得した炭治郎と対峙した際に猗窩座の目には、炭治郎の姿が植物のように見えていました。
体中の細胞が産毛に至るまで今すぐコイツを殺せと言っている
©吾峠呼世晴/集英社 コミック18巻
猗窩座ほどの強さを持った鬼でさえ、炭治郎が危険な存在であると感じ取ったのです。
炭治郎が炭十郎を植物のような人と表現したのは、穏やかで優しいという意味のほかにも、炭十郎が飛んでもない強さを持っていたという意味も含まれていたのかもしれません。
炭十郎の初登場は何話?
炭十郎が初めて登場したのは、5巻の40話「ヒノカミ」で登場します。
下弦の伍・累との戦いで窮地に追い込まれた炭治郎が走馬灯を見た際に、炭十郎からヒノカミ神楽について伝えられるシーンです。
真冬に一晩中神楽を踊り続けた炭十郎に、炭治郎はどうして長い間舞うことができるのか問いかけます。
すると炭十郎は、息の使い方について炭治郎に伝えました。
息の仕方があるんだよ
©吾峠呼世晴/集英社 コミック5巻
どれだけ動いても疲れない息の仕方
炭治郎はこのやり取りを思い出し、水の呼吸ではなく、ヒノカミ神楽で累の糸を斬ることに成功します。
炭十郎の強さ

普段は体が弱いため横になっていることが多かった炭十郎ですが、いざとなると信じられない強さを発揮しています。
その強さは、もしかしたら鬼殺隊の柱にも匹敵するのではないかとまで言われることも。
炭十郎の強さが分かるエピソードを紹介していきます。
一晩中ヒノカミ神楽を踊ることができる
先ほど少し説明しましたが、炭十郎は雪が降るほどの寒い中でも一晩中ヒノカミ神楽を舞うことができました。
炭十郎よりも若くて体力がある炭治郎でも、初めのころはヒノカミ神楽を少し使っただけで息が上がってしまい、動けなくなってしまうほどでした。
炭治郎も修業を繰り返し、少しの間ヒノカミ神楽を出せるようになりましたが、堕姫との戦いのように無理をして戦えば立ち上がることも難しい状態になってしまいます。
そんな技を炭十郎は一晩中続けることができたので、ヒノカミ神楽の習得度では炭治郎よりはるかに上だったことが分かりますね。
九尺ある熊を斧で倒す

竈門家が暮らしていた近くの山で、熊が人を食い殺すという事件が起きました。
そしてその事件の夜、事件を起こした熊が竈門家の近くに来ていると炭十郎はいち早く気づき、炭治郎を連れて家を出ます。
炭十郎たちの前に現れた熊は、九尺(約270センチメートル)もある巨大な熊で、炭十郎の倍近くはある大きさでした。
熊の迫力に炭治郎は圧倒されますが、炭十郎は落ち着いて熊に話しかけます。
しばらくして熊が炭十郎たちに近づこうとすると、炭十郎は持っていた斧で熊の首を斬り落としました。
そしてこの出来事から十日後に、炭十郎は病気で亡くなっており、病気で寿命が近かったのにもかかわらずこんな動きができるので、全盛期の時はさらに強かった可能性が高いです。

炭治郎を起こしてまで連れて行ったのは、炭治郎に見取り稽古をさせる目的があったからです。当時は炭治郎は炭十郎の意図が分かりませんでしたが、猗窩座との戦いでこのやり取りを思い出し、これが見取り稽古であったことに気づきました。
透き通る世界を会得している
炭十郎は「透き通る世界」を習得しています。
今では寒い中一晩中神楽を舞うことができる炭十郎ですが、若くて健康だった時の方が神楽を舞うことに苦戦していたみたいです。
しかし、あることを意識するようになってから神楽を辛いと思わなくなっていきました。
単純に無駄な動きが多かったんだろうと思う
©吾峠呼世晴/集英社 コミック17巻
大切なのは正しい呼吸と正しい動き
最小限の動作で最大限の力を出すことなんだ
これができるようになると、だんだんと頭の中が透明になっていき、透き通る世界が見えるようになると炭治郎に伝えていました。
死闘の中で炭治郎も透き通る世界を習得しましたが、炭十郎は戦いの中ではなく、日常生活の中で自分自身の力で習得しました。
透き通る世界を習得したのは、柱のごく一部の人たちだけなので、それを習得していたとすると、炭十郎はかなりの強さであったことが分かります。
柱と炭十郎はどちらの方が強い?
病弱ではあったものの、一晩中神楽を舞ったり九尺ある熊を斧で倒したりと普通の人間とは言い切れないほどの強さも見せている炭十郎。
鬼殺隊の最強の剣士と言われる柱と比べると、どちらの方が強いのでしょうか?
強さは柱の方が上
結論から言うと、炭十郎が柱よりも強かったという可能性は低いでしょう。
柱たちは長年稽古を積み重ねて鬼と戦い続け、かなりの実力者であり上弦の鬼たちとも渡り合えています。
しかし炭十郎は戦った経験もなく、ずっと炭売りとして生活をしていました。
熊と戦い斧で倒した経験があると言っても、いつも鬼と戦っている柱たちよりも強いという事は無いでしょう。
ポテンシャルでは柱を上回る可能性も
強さでは柱の方が上という結論になりましたが、ポテンシャルでは炭十郎の方が上かもしれません。
先ほども紹介しましたが、炭十郎は生まれて時から痣があり、透き通る世界も会得しています。
柱たちは炭治郎の痣が発現したことがきっかけで痣を発現させていたので、痣が発現したタイミングだけで考えると炭十郎の方が上ですよね。
さらに透き通る世界については、無惨との戦いの中でも会得するできたものは少なく、痣の発現よりも難しいことが分かります。
炭十郎は戦いの中で会得したのではなく、神楽を舞うときに自分の動きや呼吸方法を見直した結果、透き通る世界が見えるようになったのです。
もし炭十郎が病弱ではなく、戦うための稽古などを行っていた場合は柱たちの強さを上回ることができていたかもしれませんよね。
炭十郎の死因は?痣が関係している?

炭十郎には生まれつき額に痣のようなものがありました。
炭十郎の強さを考えると、この痣は炭治郎や柱たちが出現させた痣と同じとも考えられますよね。
そして痣を出現させると、強さを得る代わりに25歳までに死亡するというデメリットがあります。
炭治郎は炭十郎の死因は病死と言っていましたが、もしかしたら痣の寿命で体が衰弱し、若い年齢で亡くなったのかもしれません。
若いときは力もあって健康であったと思わせる発言もあり、痣の寿命が近くなってから衰弱したとも考えられそうです。
炭十郎が死亡したのは何歳?
痣を発現させると25歳までに死亡するというデメリットがありますが、炭十郎は25歳を超えても生き続けていました。
炭十郎の亡くなった年齢は分かっていませんが、物語のはじめに禰豆子がこんなことを言っていました。
六太を寝かしつけてたんだ 大騒ぎするから
©吾峠呼世晴/集英社 コミック1巻
お父さんが死んじゃって寂しいのよね
みんなお兄ちゃんにくっついて回るようになった
このことから、1話の時点で炭十郎が亡くなってからそこまで時間が経っていないという事が分かります。
1話の時点で長男である炭治郎は13歳であり、もし痣の寿命で炭十郎が亡くなっていたら炭治郎は12~13歳の時の子供という事になってしまいます。
いくら明治~大正時代でも、12~13歳の時に子供がいるというのは少し無理がありますよね。
炭治郎の年齢を元に考えると、炭十郎は30~40歳くらいで死亡したと考えられます。

炭十郎と同じく、生まれた時から痣のあった縁壱は80歳近くまで生きることができました。生まれつき痣があった人物は、25歳というボーダーラインよりも長生きができた可能性があります。縁壱は幼い時から「1日中走っても疲れない」というとんでもない体質だったので、80歳まで生きたのかもしれません。
炭十郎と縁壱の共通点と違い

炭十郎に最も近いキャラクターと言えば、同じく生まれながらに痣が発現していた縁壱でしょう。
共通点も多い2人ですが、異なる点もあります。
2人の共通点と相違点について見ていきましょう!
共通点
2人の共通点は、以下のようなものがあります。
・生まれつき痣があった
・日の呼吸を使える
・穏やかな性格をしている
・透き通る世界を会得している
・痣者とされる25歳を過ぎても生き続けた
最終的に痣が発現したキャラクターは多くいますが、生まれつき痣があったというのは炭十郎と縁壱の2人のみです。
痣は寿命の前借とされているにもかかわらず、2人は痣者の寿命である25歳を超えても生き続けているため、この2つは特に2人の共通点と言えるでしょう。
相違点
2人の共通点を説明しましたが、実は先ほどの共通点は相違点とも言えるのです。
その理由について見てみましょう。
| 生まれつき痣がある | 炭十郎は病弱であったが、縁壱は子供の時から一晩中走っていたも疲れないほどの体力があった。 |
| 日の呼吸を使える | 竈門家に代々伝わる神楽として炭十郎は使えるようになったが、縁壱は自身の力で日の呼吸を生み出し使いこなしている。 |
| 透き通る世界を 会得している | 神楽を舞い続ける中で炭十郎は透き通る世界が見えるようになったが、縁壱は生まれたときから見えており、母親の病気にも気づいていた。 |
| 25歳を過ぎても 生き続けた | 炭十郎は30~40歳ほどで死亡しているが、縁壱は80歳を超えても生き続けており、歳をとっても全盛期と変わらない剣技を見せる。 |
共通点とは言えども、2人には大きく違いがあったことも分かりますね…!
やはり縁壱は鬼滅の刃のキャラクターの中でも別格の強さを持っていました。
鬼殺隊に所属していた?

全集中の呼吸だけでなく、「透き通る世界」を取得し、さらに「痣」も発現させていた炭十郎。
鬼殺隊として十分な素質があったように思えますが、鬼殺隊とは関係性がありそうにも思えますよね。
しかし、炭十郎が鬼殺隊と関係があった、所属していた可能性はかなり低いです。
原作では炭十郎が鬼殺隊にいたという描写は一切なく、炭治郎が幼い時から病弱でした。
ヒノカミ神楽を受け継いだ炭治郎も、自分の家系は代々炭売りをしていたと言っていましたし、鬼の存在さえ知りませんでした。
もし炭十郎が鬼殺隊に所属していて鬼の存在を知っていたら、家族を守るために家に藤の花のお香を焚くなど対策もしてそうです。
鬼殺隊からの勧誘はあった?
鬼殺隊に所属していた可能性は限りなく0に近いですが、鬼殺隊からの勧誘はあったのかもしれません。
現在霞柱である時透無一郎は、隊士の中でも数少ない鬼殺隊から勧誘を受けています。
その理由は、「無一郎の祖先が始まりの呼吸の剣士」であったからです。
無一郎の可能性を感じた鬼殺隊は、杣人として生活していた無一郎を見つけ出して、鬼殺隊の当主の妻であったあまねが直々に勧誘に訪れていました。
始まりの呼吸の剣士についての手記が鬼殺隊に残っているのであれば、縁壱についての情報も残っていた可能性があります。
実際に歴代の炎柱の手記には、始まりの呼吸の剣士が身につけていた耳飾りのことが記されていました。
この耳飾りは現在は炭治郎が身につけていますが、その前は炭十郎が身につけていたため、もしかしたらその情報を頼りに竈門家に訪れていたかもしれません。
しかし炭十郎はすでに病弱で家族もいたため、鬼殺隊として人々を鬼から守るのではなく、1番大切な家族を守る為に勧誘を断った経緯があってもおかしくないですよね。
まとめ

炭治郎と禰豆子の父親・炭十郎について解説しました。まとめると…
・炭治郎と禰豆子の父親で、物語が始まった時点ではすでに故人である。
・初登場は5巻の40話「ヒノカミ」で、炭治郎の走馬灯の中で登場。
・病弱でありながら、一晩中ヒノカミ神楽を舞うことができる。
・病死する10日前、九尺もある熊を斧で倒す。
・生まれつき額に痣があり、透き通る世界も習得している。
・柱の方が強いが、ポテンシャルはかなり高い
・痣の寿命で亡くなった可能性が高いが、亡くなったのは30~40歳くらい。
・過去に鬼殺隊に所属していた可能性は低いが、勧誘はあったかもしれない
柱でさえも当初は取得していなかった透き通る世界や、痣の発現もできていた炭十郎。
すでに故人ですが、炭治郎がピンチになったときに何度も回想で登場し、救ってくれています。
鬼殺隊に入ったことはなさそうですが、もし鬼殺隊に入隊していたら、縁壱のような存在になっていたかもしれませんね。
ここまでお読みいただきありがとうございました!
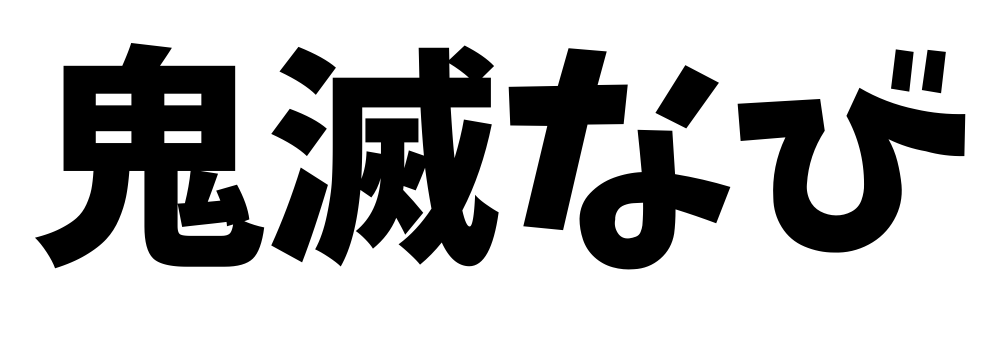
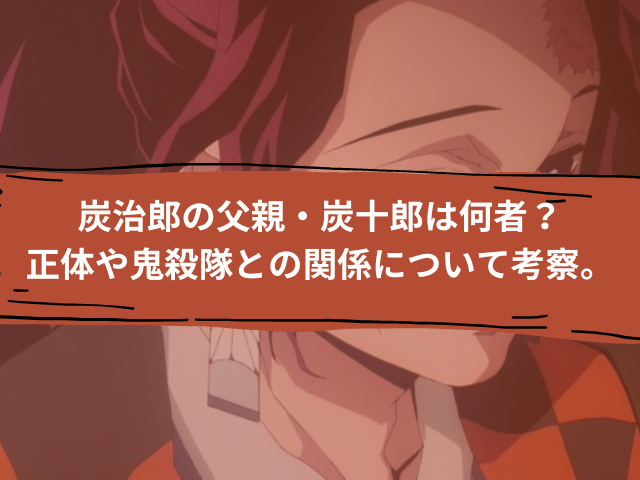
関連記事