初登場時は常に何かに怯え、上弦の鬼としての風格がまったくと言っていいほどなかった半天狗。
しかし柱を2人で22人も殺している堕姫や妓夫太郎よりも上である肆の数字をもらっていることから、かなりの実力者であることが分かります。
また普通の鬼とは違い、分身の鬼の首を斬ってしまうと、さらに分身が増えてしまうという厄介な能力を持っており、炭治郎たちは討伐にかなり苦戦していました。
半天狗は人間だった頃のことを覚えていませんが、死ぬ直前に自分の人間時代を思い出したのです。
過去については原作で詳しくは描かれていませんでしたが、描かれたわずかな情報だけでもまともじゃない人生を送っていたことが分かりました。
そこで今回の記事では、半天狗の過去について詳しく解説していきます!
- 半天狗の過去とは?
- 半天狗の人間時代がクズと言われている理由は?
- 人間の時も鬼の時と同じように臆病者だったの?
などが気になる人は、ぜひこの記事を読んでみてくださいね。
▼▼▼動画でもご覧いただけます▼▼▼
半天狗(はんてんぐ)とはどんなキャラクター?

半天狗は、単行本12巻の第98話「上弦集結」で初登場します。
見た目は小さな老人のようで、無惨が機嫌が悪い様子を前面に出した際には1人だけ「ヒイイッ!」と怯えた様子でした。
上弦の鬼であるので強いのは確かですが、あまり威厳は感じられない鬼ですよね。
過去を解説する前に、鬼となった半天狗について解説したいと思います。
上弦の肆で、常に怯えた様子でいる
半天狗は上弦の肆の数字をもらっており、少なくても100年以上は上弦の鬼の立場を守り続けています。
無惨に怯えるのは分かりますが、猗窩座が童磨を殴った時も怯えていましたし、鬼殺隊と遭遇した時にも悲鳴を上げていたことから、何に対しても恐ろしいと感じてしまうみたいです。
こういった行動を取るのは、自分は力のない弱い者で被害者であると常に思っていることが原因です。
若いころの自分の姿をした分身を生み出して戦う
半天狗は、若いころの自分の姿をした分身を生み出し、その分身たちに戦わせます。
分身は首を斬っても死ぬことはなく、むしろ首を斬ると分身がさらに増えるという厄介な性質を持っており、本体の首を斬らないと意味がありません。
分身たちはそれぞれ舌に「喜怒哀楽」と書かれており、それぞれ異なった力を持っています。
半天狗が生み出す喜怒哀楽の分身たちを紹介します。
空喜(うろぎ)

分身の中で一番人からかけ離れた姿で、背中に翼が生えていたり手足が鳥のような作りになっています。
空を飛ぶこともできて、防御することが出来ない超音波での攻撃もしてきます。
戦いを楽しむ癖があり、油断することが多いのが欠点です。
積怒(せきど)

他の分身たちに指示を出したりと、まとめ役のような立ち位置で冷静に戦況を分析します。
雷を発生させる錫杖(しゃくじょう)を持っており、致命的なダメージを与える程の威力はありませんが、広範囲に電撃を発生させるため相手をしびれさせて動きを止めることが出来ます。
分身たちが追い詰められると、他の三体(空喜、哀絶、可楽)を吸収して憎珀天へとなります。
哀絶(あいぜつ)

性格は積怒に似ており、冷静で隙を見せることはあまりありません。
体術を得意として、槍を使って技を繰り出すいシーンもありました。
喜怒哀楽の分身たちの中で、技を出していたのは哀絶のみになります。
可楽(からく)

戦いを楽しむ喜怒哀楽の中で一番の戦闘狂です。
葉の団扇(うちわ)を持っており、仰ぐと人を簡単に吹き飛ばすことができます。
しかしこの団扇は誰でも使用することが出来るため、戦っている相手に利用されてしまうことも。
憎珀天(ぞうはくてん)

積怒が他の3人を吸収すると生まれる半天狗の最強の分身です。
喜怒哀楽の鬼の中で一番見た目が若いですが、姿を見ただけで玄弥が手足に力が入らなくなるほどの威圧感を放ちます。
本体である半天狗を「弱い者」、半天狗を倒そうとする鬼殺隊を「極悪人」として自分がすることを正当化するような発言をします。

吸収した喜怒哀楽の鬼の力の全てを使うことができ、分身たちよりもはるかに強い力を持ちます。ですが憎珀天も分身の鬼のため、憎珀天の攻撃を躱しながら本体の首を斬らないと倒すことが出来ません。
半天狗本体
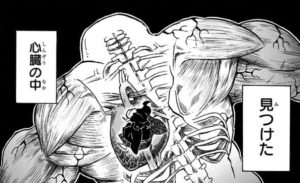
本体の体はとても小さく、見つけ出すだけでもかなり困難です。
玄弥は自力で見つけ出すことが出来ず、鼻が利く炭治郎がいて何とか見つけ出すことが出来ました。
さらに体が小さいにも関わらず首はかなり硬く、首を斬ろうとすると日輪刀が折れてしまうほど。
しかし弱点もあり、本体は戦闘力はほぼなく、分身を生み出せば生み出すほど体力が消耗していきます。

半天狗の本体は戦闘能力は全くないかわりに、逃げる能力がすさまじく高いです。逃げるときはその体のサイズからは想像もできないほどの速度で走ります。
無惨からはうざいと思われることも
分身を生み出すというやっかいな血鬼術を持っている半天狗ですが、無惨からはお気に入りとされているわけではなく、普通という評価でした。
ただいつも怯えた様子で悲鳴を上げているため、それがたまにうざいと思っているみたいです。
ですが、最期に太陽を克服した禰豆子の姿を無惨に共有したことで、滅多に他人を褒めない無惨から称賛されていました。
半天狗の過去や人間時代

ではいよいよ半天狗の過去について詳しく解説していきます!
半天狗の性格は、鬼の時と同じだったのでしょうか?
小心者であったが、幼い頃から悪事を働いていた
昔から嘘つきで、物事を自分の都合のいいように解釈する歪んだ性格でした。
子供の時から鬼の時と同じで気弱でしたが、やられた分はしっかり仕返しをしています。
さらに仕返しをするときは、絶対にやったのが自分だと分からないようにしていました。
結婚して妻と子供がいた時もあった
仕返しが自分だとばれないように、自分の名前、年齢などを何度も変えて答えていたため、自分の本名でさえも忘れてしまっていました。
しかしそんな半天狗にも、妻や子供がいた時があったみたいです。
ですが関係は良好ではなく、半天狗は妻から不誠実さを責められ続けた結果、逆切れして妻子を殺害してしまったのです。

妻子を殺害した時でさえ、家族に理解してもらえない自分は可哀そうな人とおもっていたようです。半天狗の被害者意識は異常ですね…
目の見えない老人を演じるようになる
老齢になってきたある日、半天狗はガラの悪い男とぶつかってしまいます。
その時にとっさに目の見えない老人を演じたところ、男から見逃してもらえました。
そのことに味を占めた半天狗は、健常者であるにも関わらず、盲目の老人の振りをするようになったのです。
すると善意で半天狗を世話してくれる人々が現れ、半天狗はますます気を良くしていきます。
半天狗は善意で世話をしてくれる人々につけこみ、盗みと殺人を繰り返すようになったのです。
悪事がばれ、告発しようとした男を殺害
悪事を働いていた半天狗ですが、同じ盲目の男に半天狗の悪事がばれてしまいます。
盲目の男は半天狗の今までの行動に憤りを感じ、半天狗を告発しようとしました。
すると半天狗は告発を阻止するために、盲目の男性を殺害したのです。

半天狗から盗みをされた人の中には、半天狗の盗みを責めず、知らないふりをしてくれた人もいいたみたいです。それなのに半天狗は悪事をやめようと考えたことは一度もありませんでした。
奉行に嘘を見抜かれ、打ち首に
告発しようとしていた盲目の男を殺したことにより、半天狗の今までの悪事が次々と明らかになりました。
罪を少しでも軽くしようと半天狗は弱い者を演じますが、担当の奉行にそれが嘘であると見抜かれてしまいます。
本性を見抜かれた半天狗は、今までの罪を償うために打ち首になることが決まりました。

奉行に嘘を見抜かれても、半天狗は目が見えない老人を演じ続けました。それどころか、「自分は悪くない、この手が勝手にやった」と最後まで罪を認めませんでした。
首を斬られる直前に人間の記憶を思い出す
半天狗は、人間だった頃の記憶がありません。
ですが、追い詰められて炭治郎に首を斬られる直前に、人間だった頃の記憶が走馬灯のように駆け巡りました。
玉壺は最後まで人間だった頃の記憶を取り戻すことはありませんでしたが、半天狗は最後の最期で人間だった頃の記憶を取り戻していたようです。
半天狗が鬼になった理由
半天狗は鬼になった理由は、打ち首になる予定だった時にたまたま無惨が居合わせ、その時に鬼にしてもらったからです。
鬼となった半天狗は、自分を裁こうとした奉行を報復として殺害しています。
半天狗は鬼になって記憶は無くなったはずですが、鬼になった直前は人間だった頃の記憶を持っていたのかもしれませんね。
まとめ

半天狗の過去や、人間時代について解説しました。まとめると…
・子供の時から嘘つきで、物事を全て自分の都合が良いように解釈していた
・悪事を重ねて自分を偽っているうちに、自分の本名が分からなくなってしまった
・妻や子供がいた時もあったが、妻に不誠実さを咎められると逆切れして妻子を殺していた
・目の見えない老人の振りをしたら周囲の人たちが優しくしてくれたので、それに付け込み悪事を働くようになる
・盲目の男に悪事がばれてしまい、口封じのために盲目の男を殺害する
・盲目の男を殺害したことで悪事がばれ、担当の奉行により打ち首が決定する
鬼の半天狗も被害者意識がかなりひどかったですが、人間の時から同じくらい外道であったことが分かりました。
その性格は戦いの中にも表れており、戦いは分身たちにさせておいて本人はただ逃げるだけでしたね。
あの優しい炭治郎でさえ、半天狗のことを「性根のねじ曲がった悪鬼」と言っていました。
ここまでお読みいただきありがとうございました!
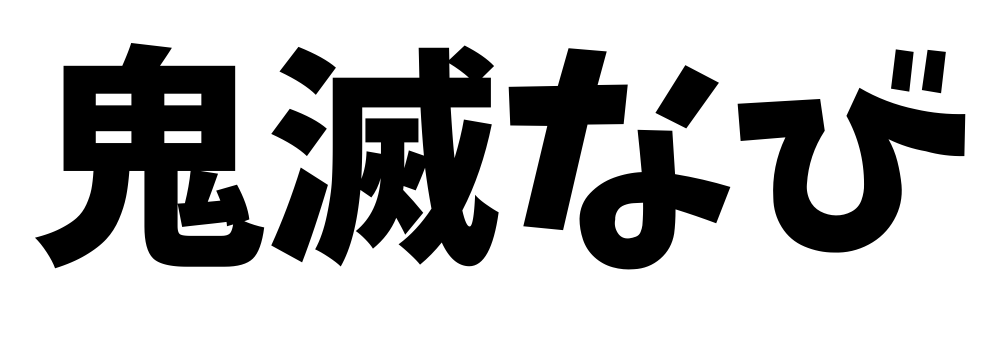
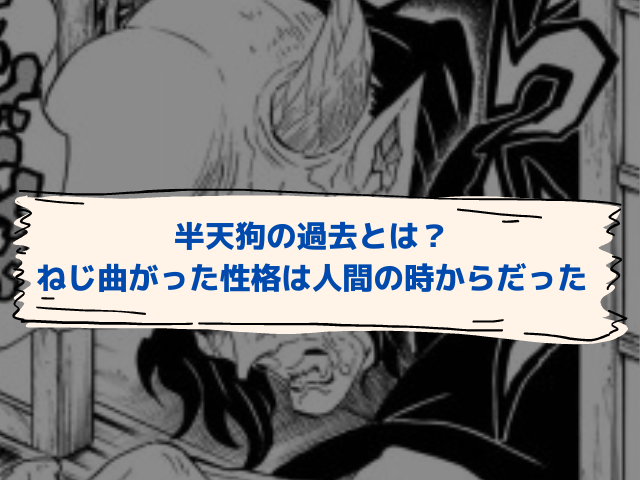
関連記事